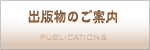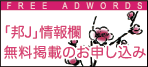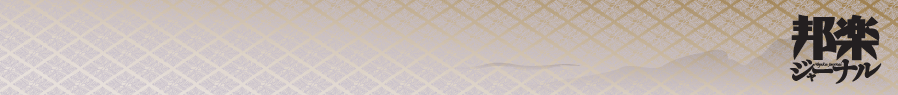邦Jと邦楽界のあゆみ
- 邦楽ジャーナルの始動!・・・そのころ
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
邦楽ジャーナルの始動!・・・そのころ
1987年1月末日、邦楽ジャーナルは産声を上げた。本文16ページ。記事、写真、写植指定、版下製作、すべて手作りだ。ある演奏会場に並べたら、宣伝用のパンフレットと間違えられて持っていかれたこともあった。だが、こんな雑誌でも、形にできたことは無上の喜びだった。創刊号を前に狭いアパートの一室で友人や妻たちとカンパイしたときの幸福感を思い出す。31歳だった。
「これから始まる」という緊張感もあった。ただ、先行きのことはほとんど考えていなかったように思う。「自分が必要と思うもの、面白いと思うものを出せば、文章は稚拙でもきっと読者は喜んでくれる」と信じ、ページはなくとも中身で勝負!と意気込んでいた。
創刊号のメイン記事、人物コーナーでは「沢井一恵」を取り上げた。当時いちばん輝いてみえた。 「沢井忠夫」ではなかった。忠夫氏は組織固めに汲々としているようにみえた。そういう時期だったのだろう。だが、そんな忠夫氏があったからこそ一恵氏の自由奔放な活動が出来たと、いま思う。「なんで創刊号に忠夫さんや尺八3本会じゃないんだ!」と言われたこともあった。だが、「既成概念にとらわれず、自分の目を大切にしたい。邦楽ジャーナルとはそういう雑誌だ」そんな決意をあらわすものでもあった。
一恵氏はインタビューのなかで言った。「呼んでいただいた会はやっぱり責任をとりきってないと思う」。だから、ひとりで箏をかついで出掛け、主催者と一緒になってコンサートを作り上げる「箏遊行」を展開した。創刊号で眼光鋭い写真を掲載した。当時の他の邦楽紙誌が「権威を大事に」「お互いをほめあって」「波風立てず」「笑顔」の誌面作りをするのなら、真っ向から対立するものを作りたかった。「そういう状況ではないだろう」という思いがあったから。急激に冷え込んできた邦楽界に業界関係者は危機感を抱いていた。
「一恵さんがここまで言うのなら私も言う」と、第2号以降続くインタビューは(当時としては)過激なものになった。おかげで「危険な雑誌」というありがたいレッテルをはられ、「あんなところに広告は出すな」というおふれまで回ったようだ。これは最高の宣伝になった。
本誌にタブーはない。これまで、触れてはいけない暗黙の了解事項であった「家元制度の是非」もテーマに掲げた。読者も参加しての力のある誌面となった。
創刊当時の邦楽界が保守的だったかというと、そうでもない。冷えた熱をなんとかしなければと、演奏家はより自由で気軽な雰囲気を醸し出すコンパクトな会を開くようになった。沢井一恵、野坂惠子(現・操壽)、宮下伸、山本邦山、砂崎知子といった大御所も、尺八1979、日本音楽集団や沢井箏曲院の若手も、小さな空間で「ミニコンサート」や「サロンコンサート」をシリーズで行った。今でいう「ライブ」だ。「演奏会=おさらい会あるいはホールコンサート」という構図からの脱却だった。
尺八の大御所・横山勝也氏は88年、「尺八音楽は流派のものにあらず。すべての愛好者の財産である」と、私財を投げ打って岡山に国際尺八研修館を開設した。これがもとになって、流派はもとより人種をも超えた国際尺八フェスティバルが世界で開かれるようになっていく。94年の岡山に始まり、98年ボルダー、02年東京、04年ニューヨーク、08年シドニーと続く。規模の小さな国際尺八フェスティバルは、いまや毎年、世界6大陸のどこかしらでやっているという具合だ。
作曲のほうに目を転じよう。非常にマニアックになってきた現代邦楽に異を唱えるように、若手が自分の感覚で作った作品を世に問うようになった。どれもメロディアスな楽曲。箏の吉崎克彦の作品は2、3年で知られるところとなり、90年には邦楽ジャーナルで「シンデレラボーイ」と呼んで記事にした。88年に発足した尺八・箏・ギターの「遠音」は北海道の大自然をテーマに清々しい作品を世に送り出した。それは少しずつ知られ、20年経った今では、CDが数万枚売れるロングセラーとなっている。90年代に入ると、折からの「ワールドミュージック」ブームも手伝って、ジャンルを超えた様々な邦楽グループが生まれるようになり「邦楽ニューウェイブ」という言葉を生むに至った。「遠音」や箏と尺八のトリオ「箏座」はその先駆けだった。
楽器も新しい発想のもとで様々誕生した。90年には「エレクトリック箏」を「遠音」が、「エレキ三味線」を三味線かとうが開発。これによってバンド活動での音量・音質の苦労が払拭され、音楽作りの自由度が増した。91年には野坂惠子が25絃箏を発表し、これも音楽の幅を広げ、現在では若手を中心に様々なジャンルで使われるようになっている。
簡便な楽器も登場する。97年、合成樹脂尺八「なる八くん」を開発したのは菅原久仁義氏。安くてよく鳴り、割れないことが評判となって人気商品となった。95年、箏では金沢の麻井紅仁子氏が120cmのペグ付き箏「NEO-KOTO」を、全音楽譜出版が86cmの「文化箏」を発売した。両者とも家元制度とは違った組織を創設して発展していく。同時に、「なる八くん」もそうだが、和楽器が導入される学校教育にも少なからず影響を及ぼした。
教育界は一大変革が起きたときだった。87年に「音楽教育を考える国民会議」、88年に「邦楽教育を推進する会」が設立され、小中学校に邦楽教育を導入しようと、23万人の署名を集めた。その年の7月、文部省から「日本の伝統音楽重視」が打ち出され、やがて02年から中学校での「和楽器必修」へと結びついていく。
太鼓ブームが起きたのも創刊のころだった。88年の「1億円ふるさと創生」政策にものって、全国各地に組太鼓のグループが出来た。津軽三味線は90年代に木下伸市(現・木乃下真市)や上妻宏光らのオリジナルで脚光を浴び、21世紀に入るとその下の世代である吉田兄弟が登場して一気に火がついた。
スターとしては95年ころから活躍し始めた雅楽師・東儀秀樹が注目をあつめ、癒しの音楽として「雅楽」も同時に一般の目に触れるようになった。現在、尺八の藤原道山がホリプロ所属となり、様々なメディアに登場している。
「情報と本音の雑誌」を売り言葉に邦楽ジャーナルは始まった。その時々に起こっていることの重要性を考え、上記のような事柄を様々な手法で記事にしてきたが、ジャーナルの誕生は、いま思えば、変革のときにあって、必要なときに必要な雑誌が出現した、ということかもしれない。当初は「失敗する」とほとんどの人に言われたものだが、読者をはじめ多くの人の応援があって今日まで続けてこられた。深く感謝している。
「邦楽界の20年の歩み」を以下に記した。今日に至るまでにどういう流れがあったのか、ご覧いただきたい。そして、これからどうなるのか・・・。邦楽の歴史は私たちみんなが作って行くもの。「どうなるのか」ではなく、「どうするのか」ということを多くの人と語り合いたい。
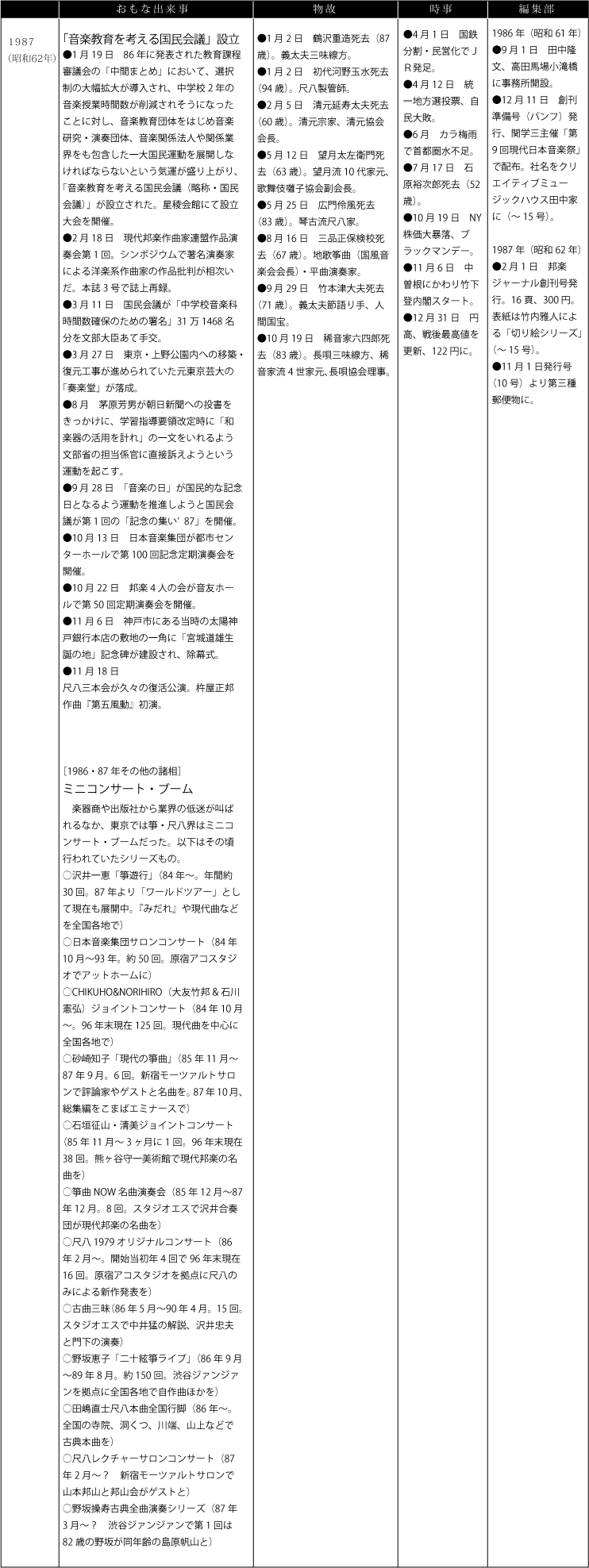
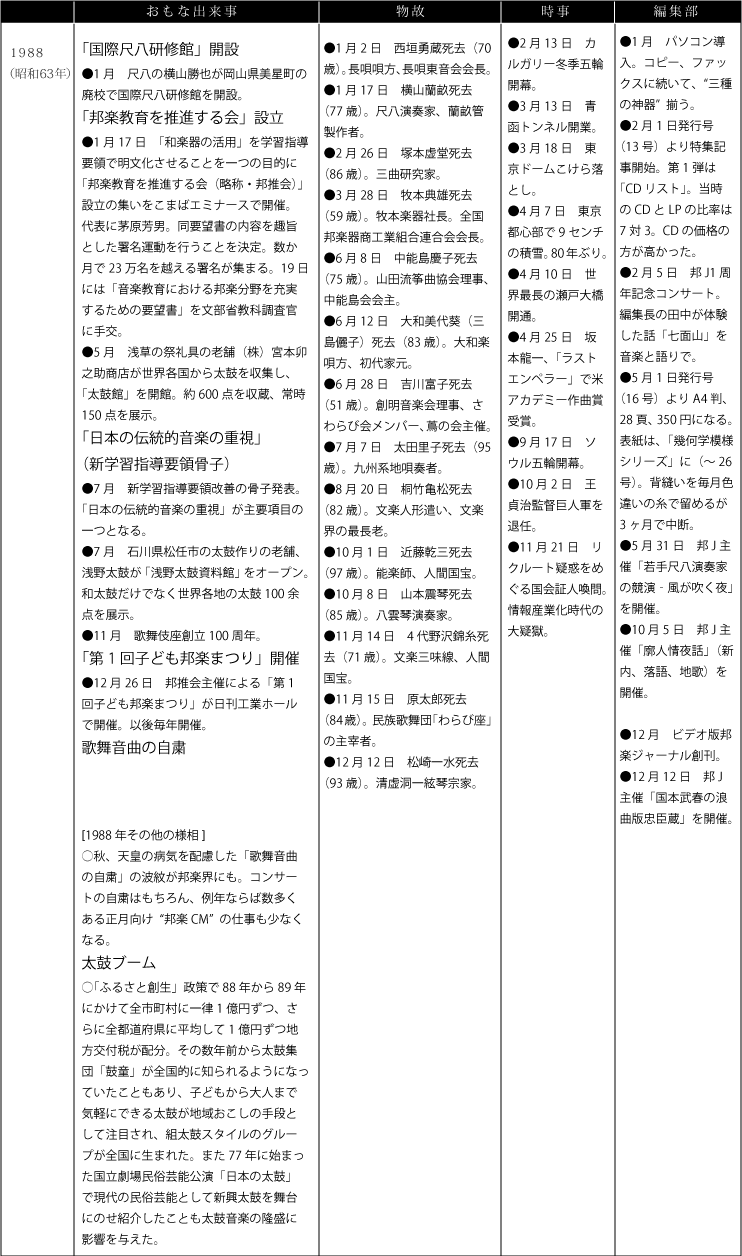
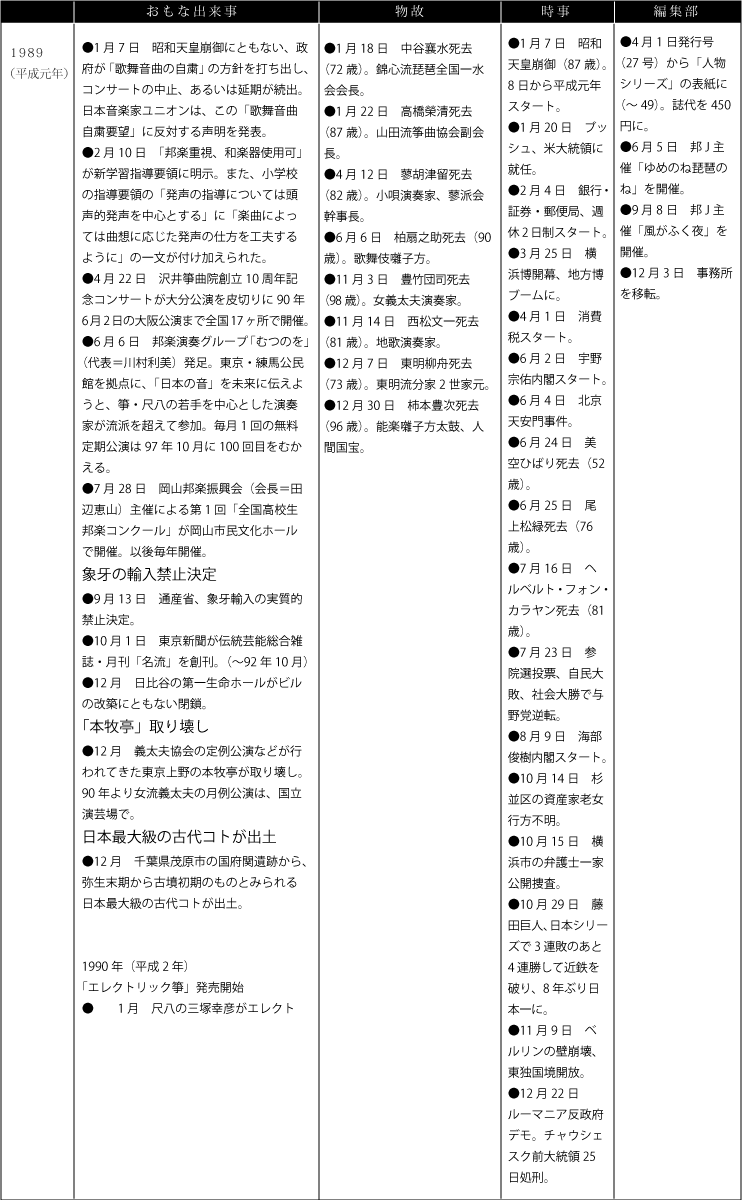
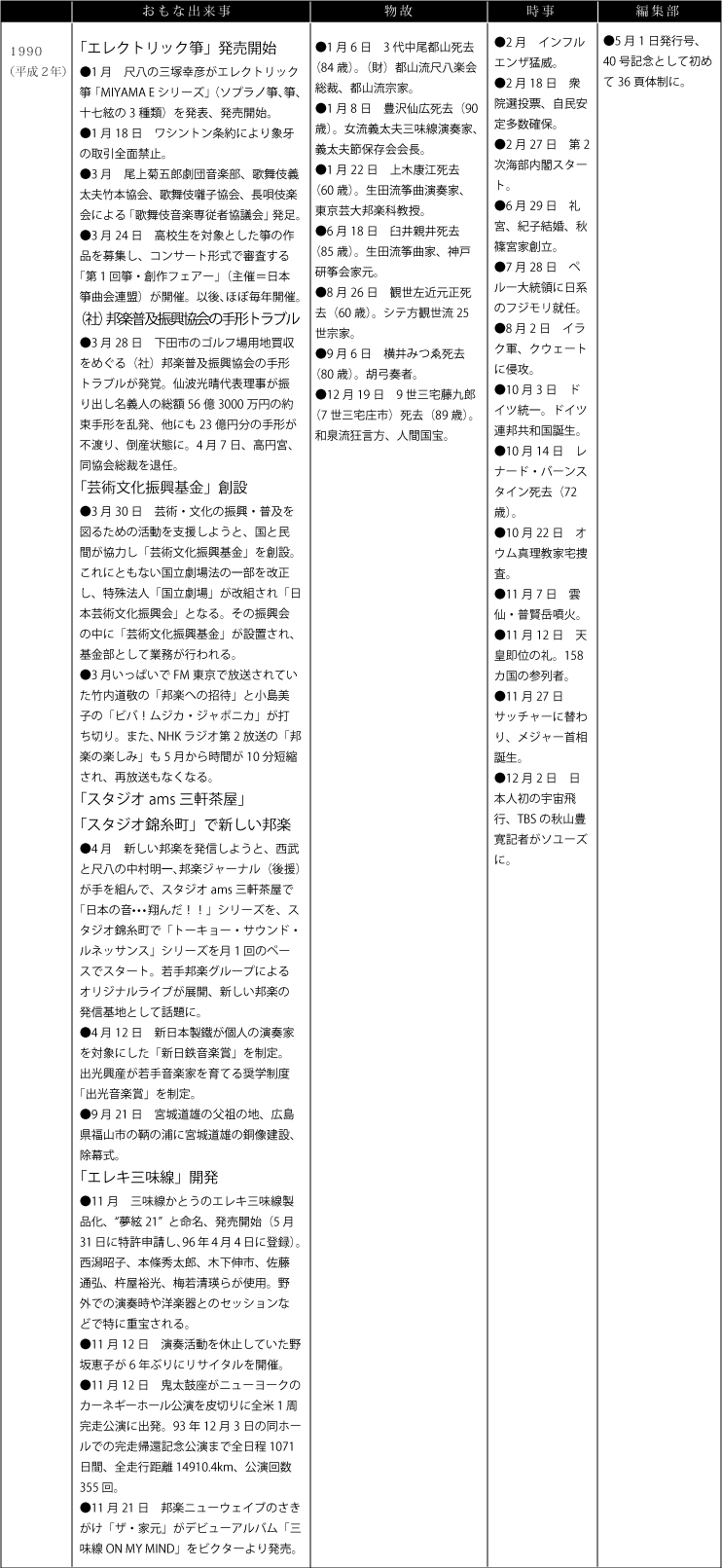
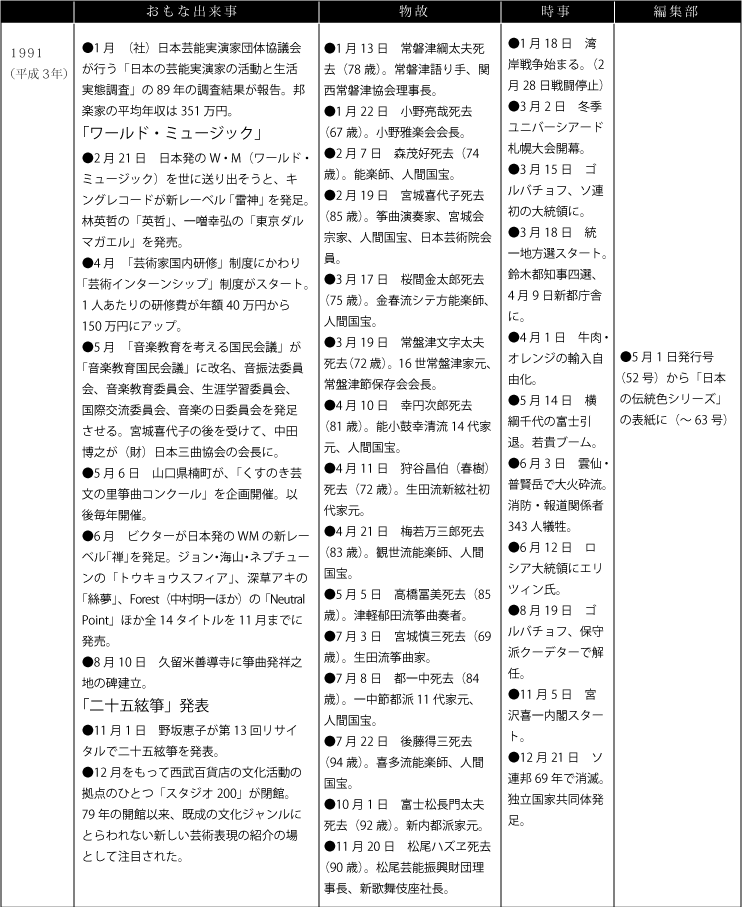
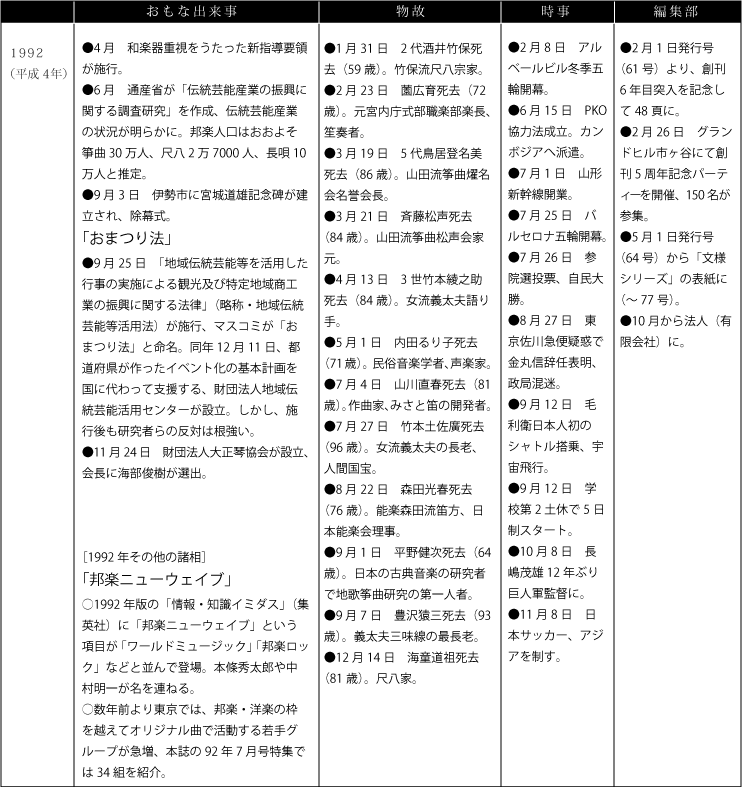
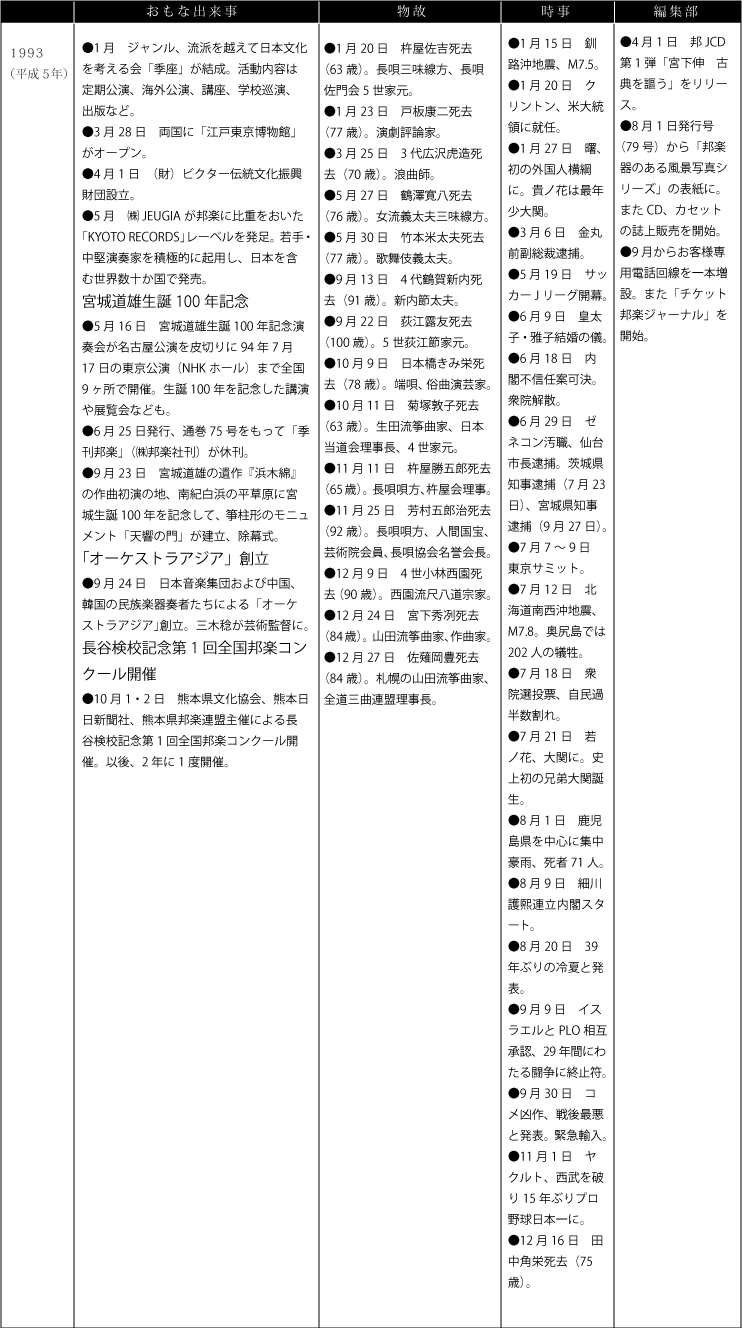
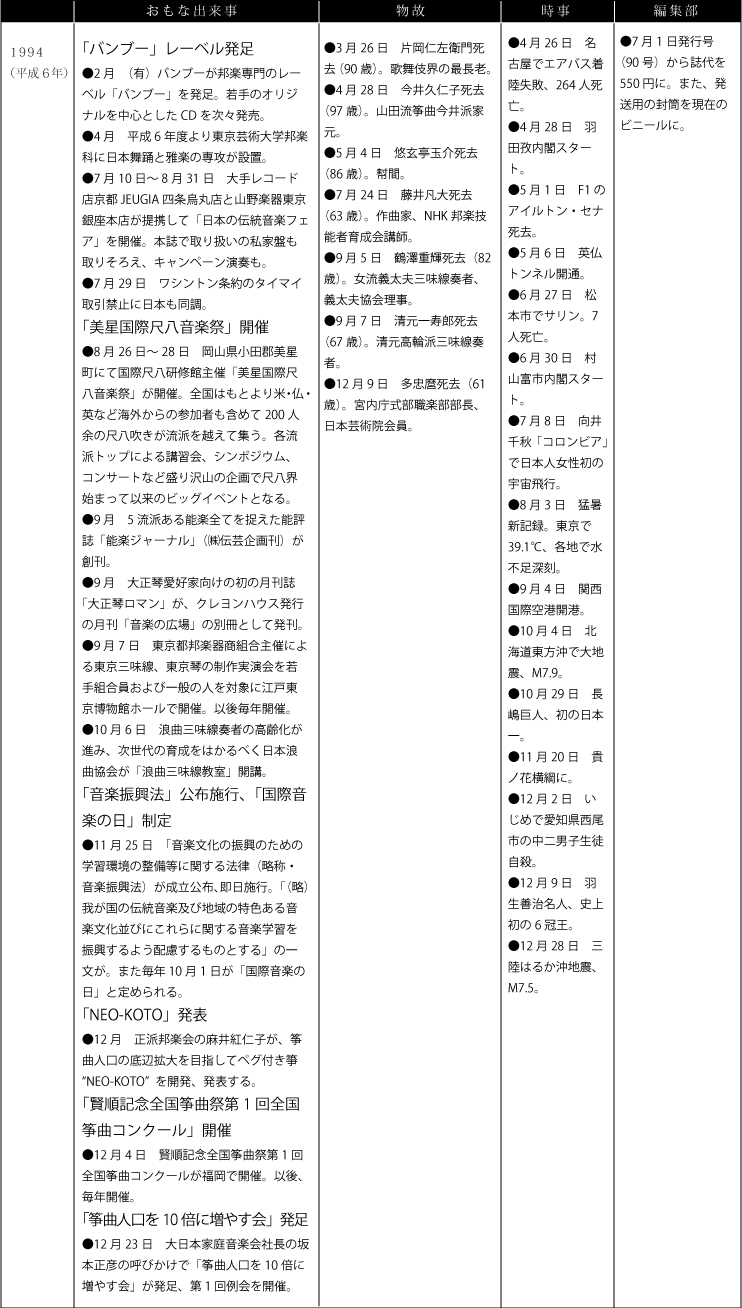
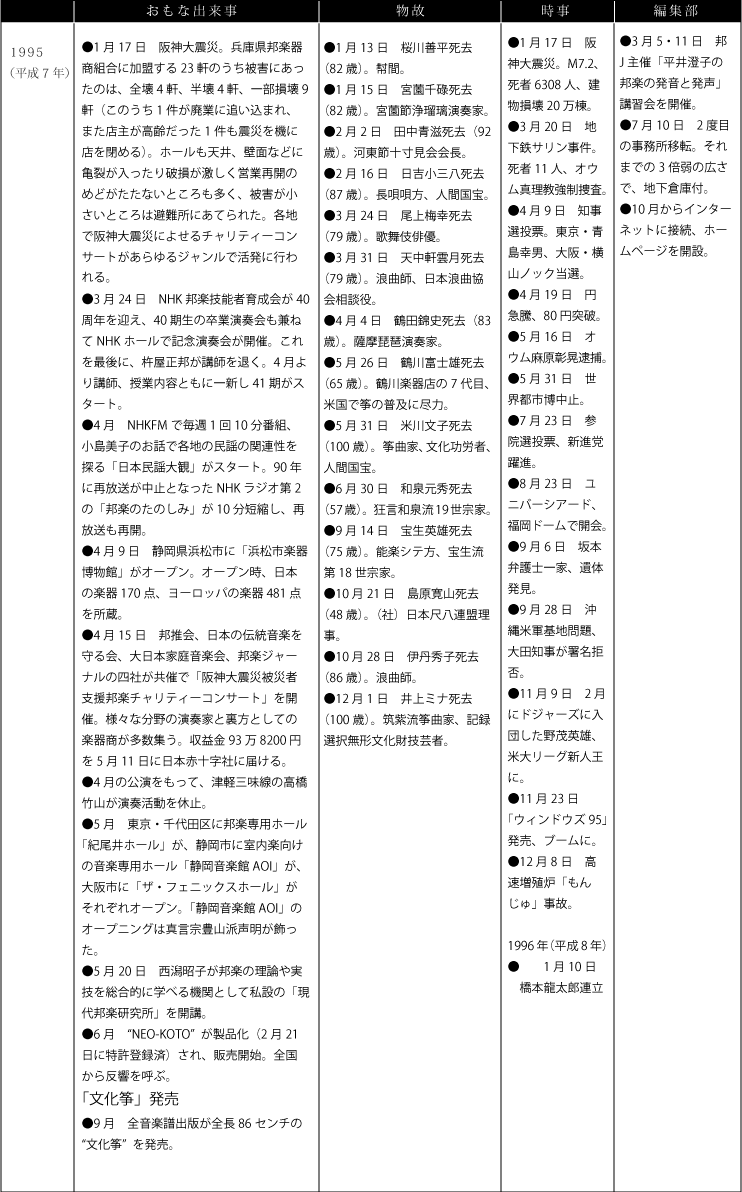
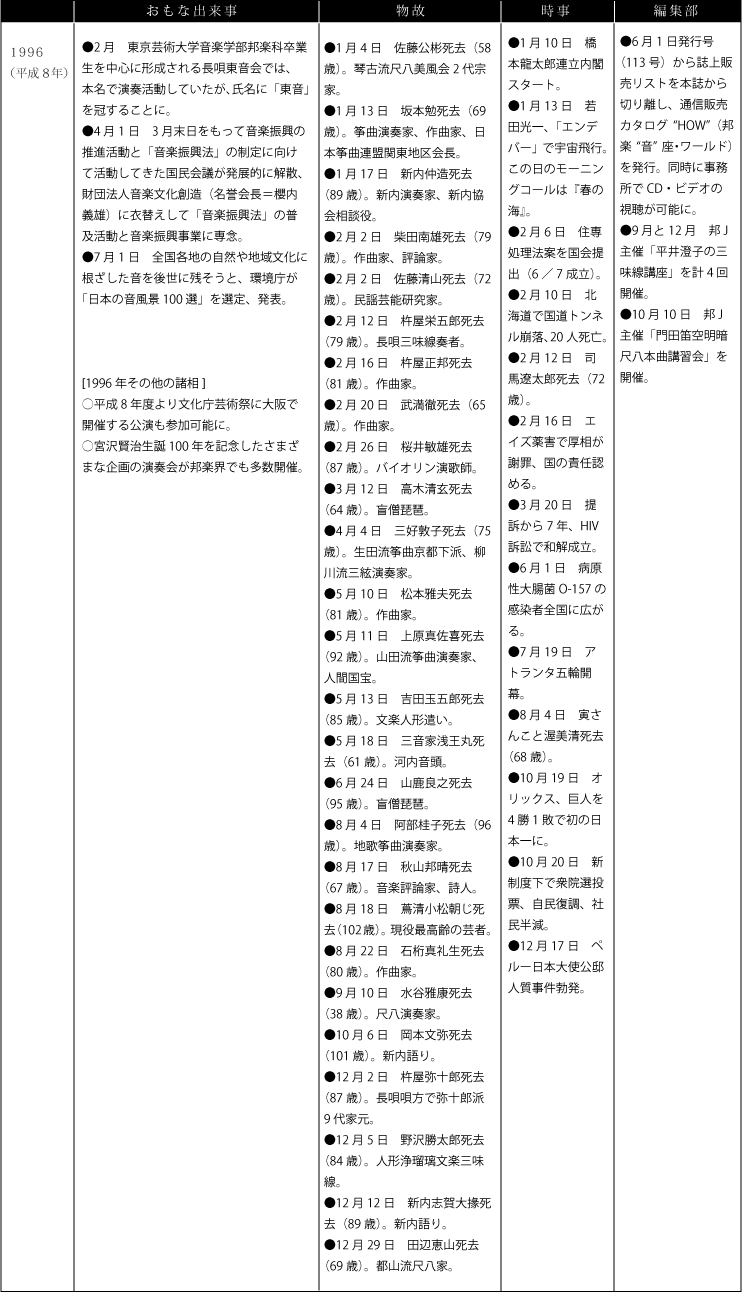
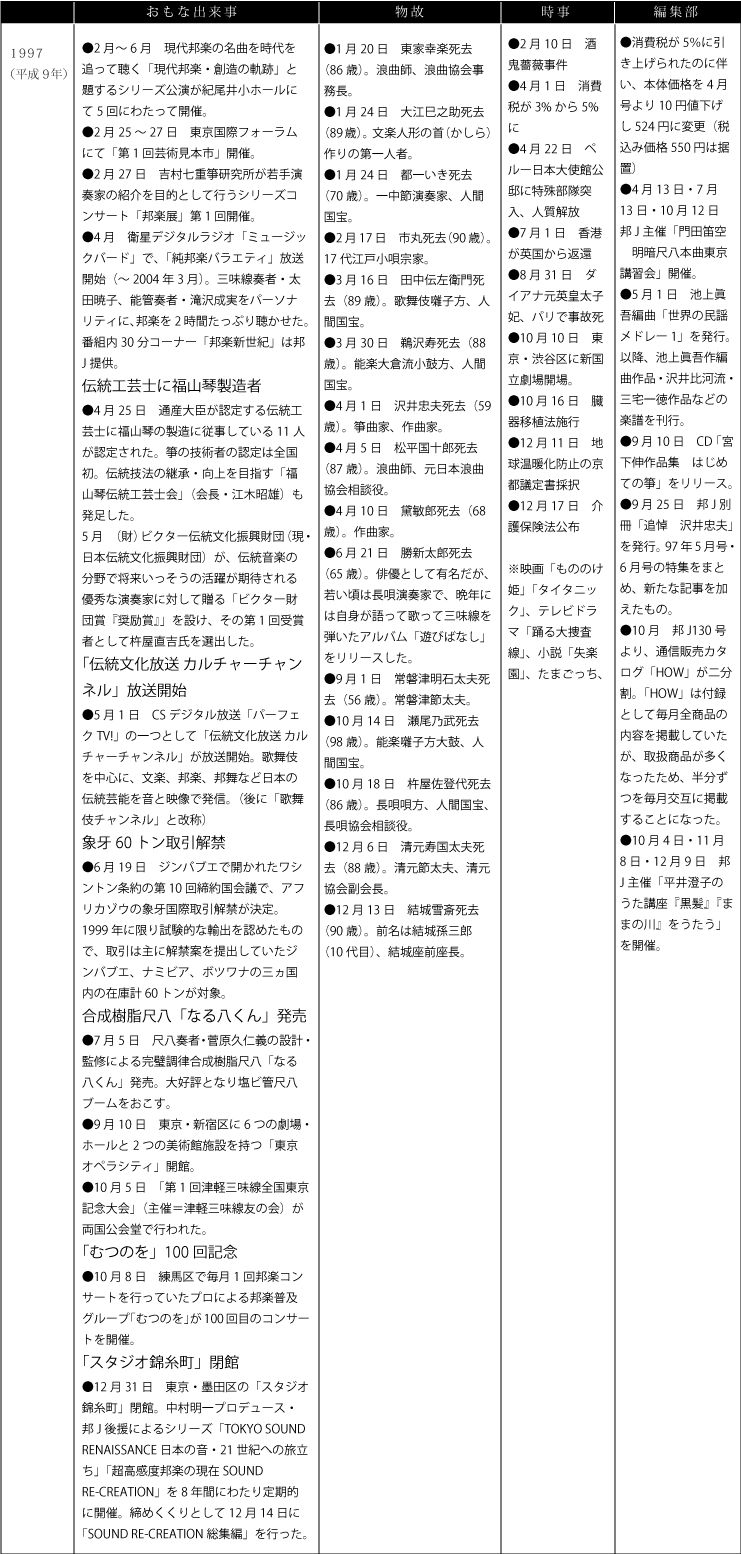
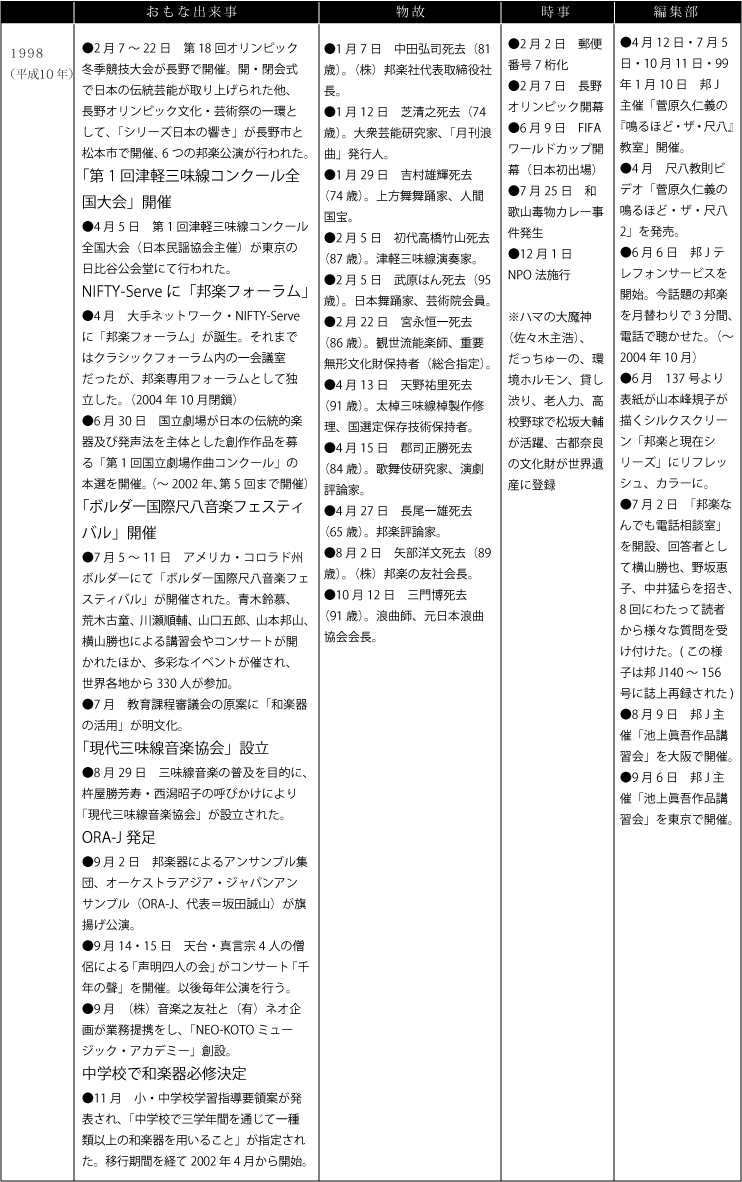
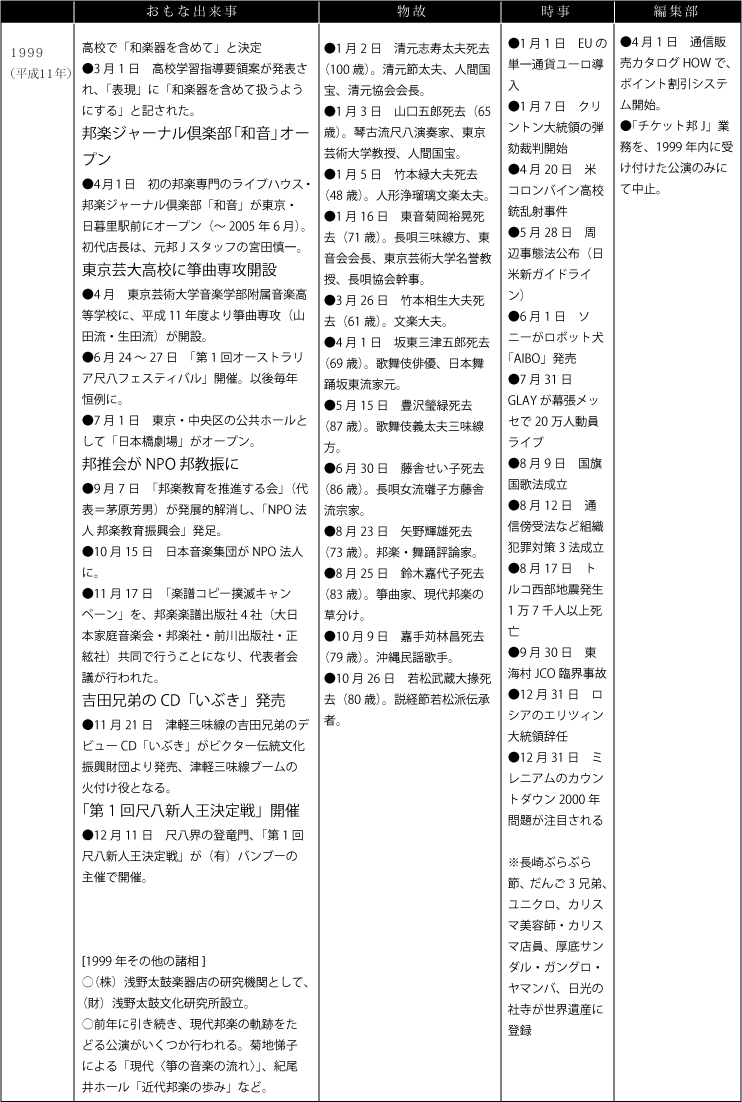
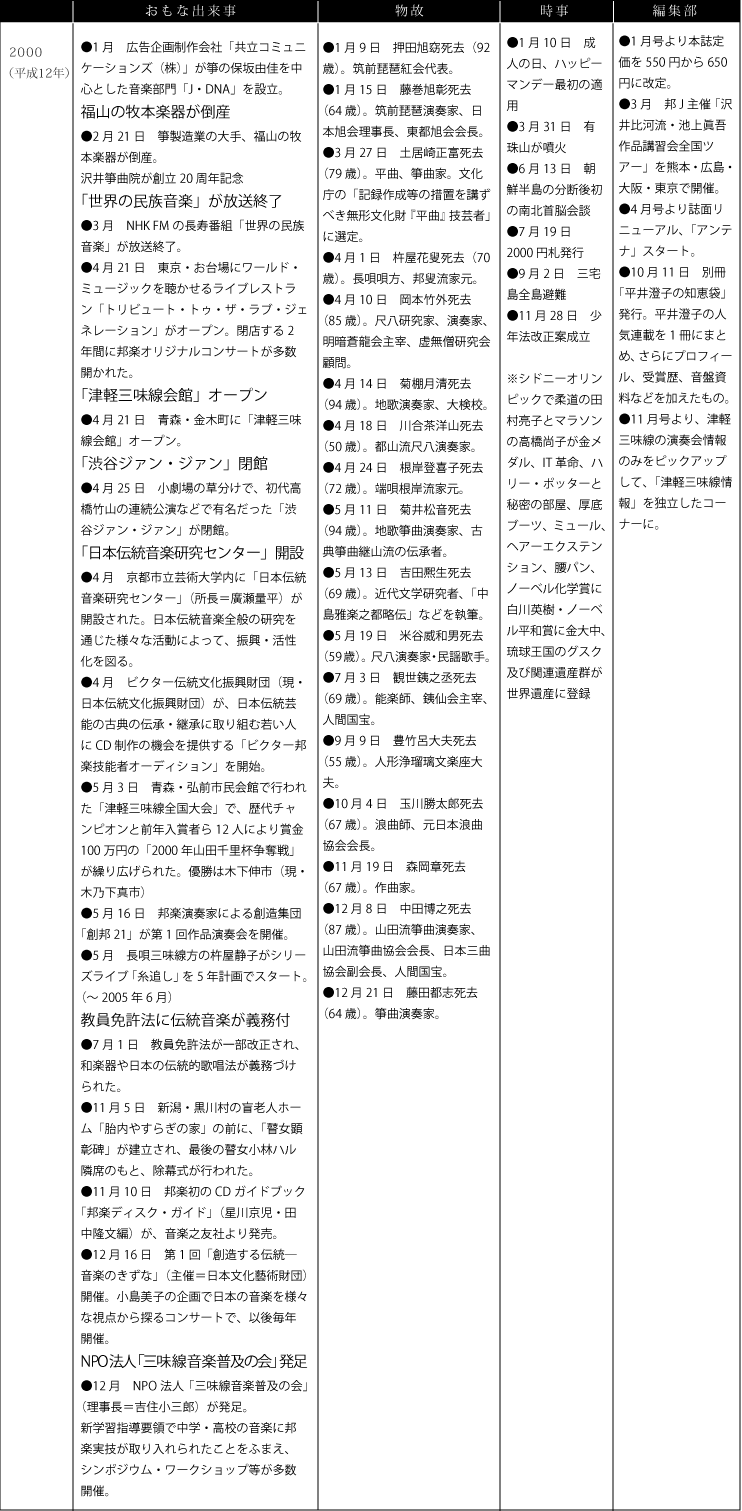
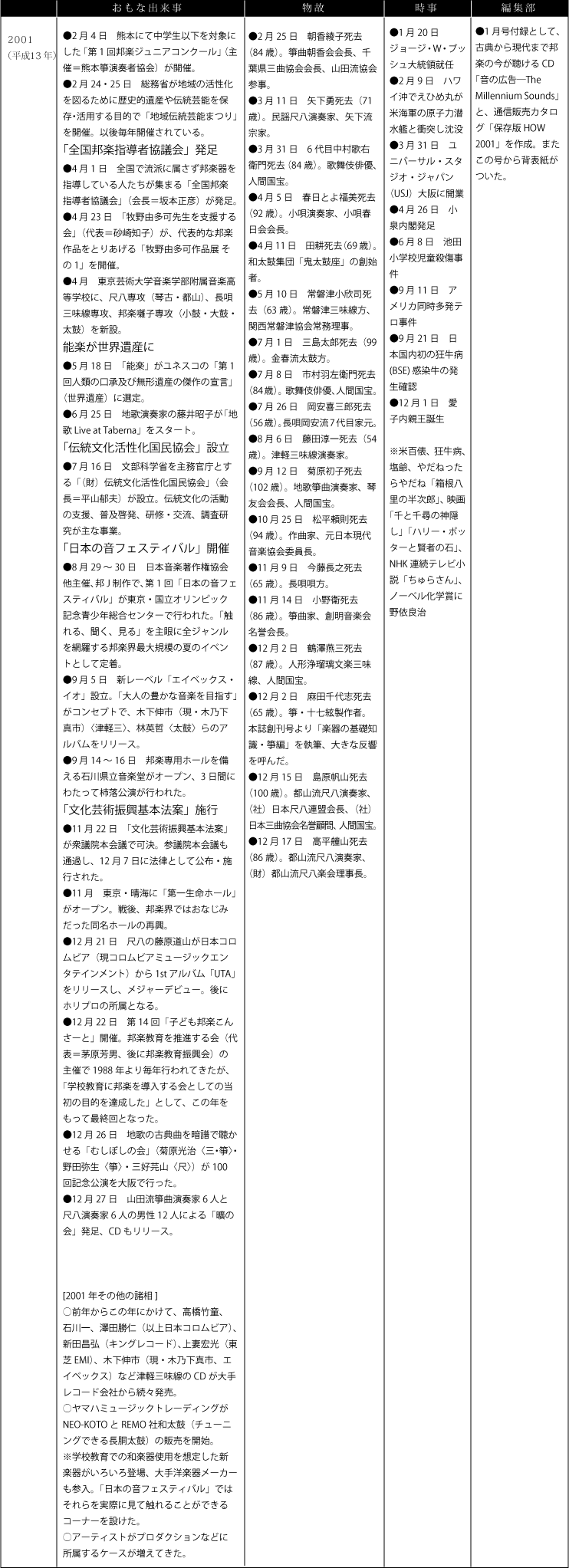
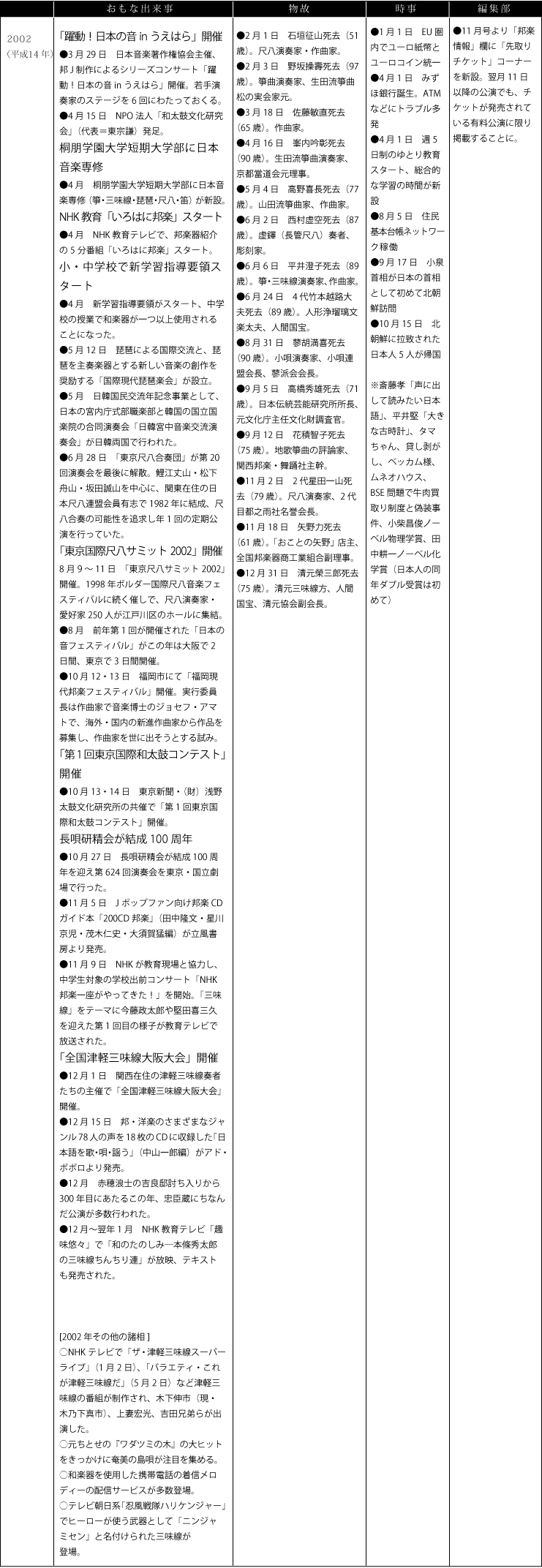
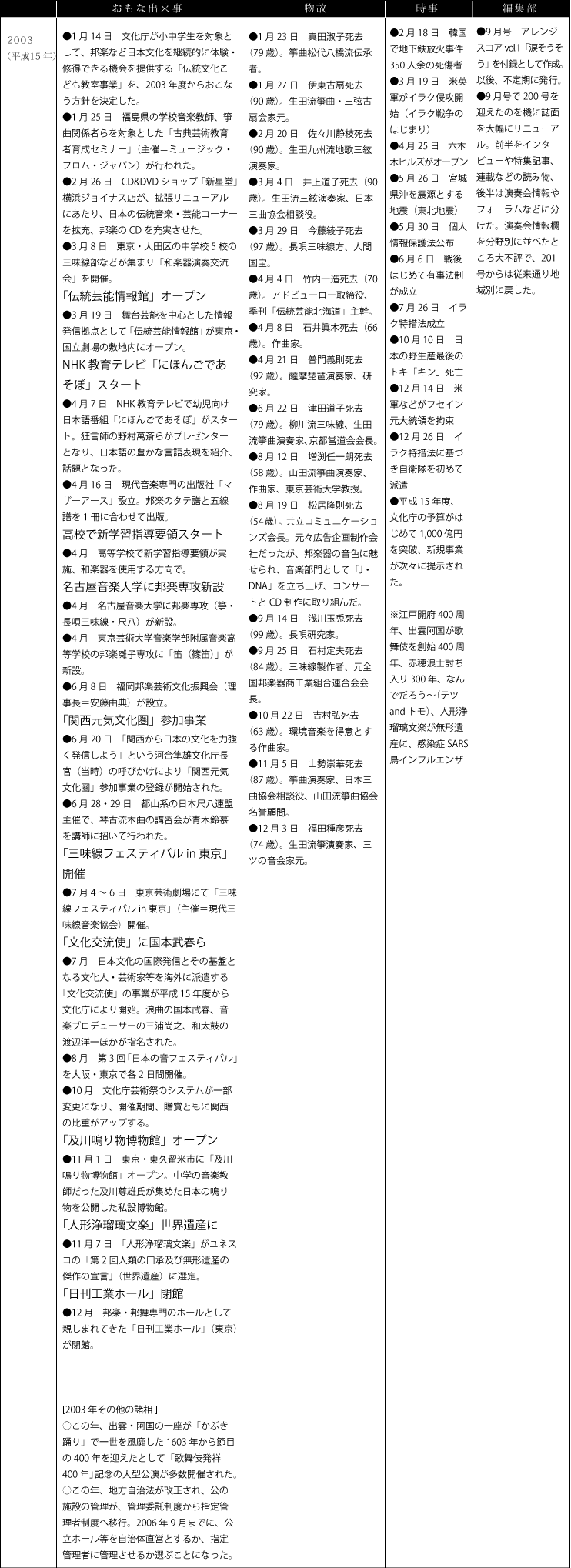
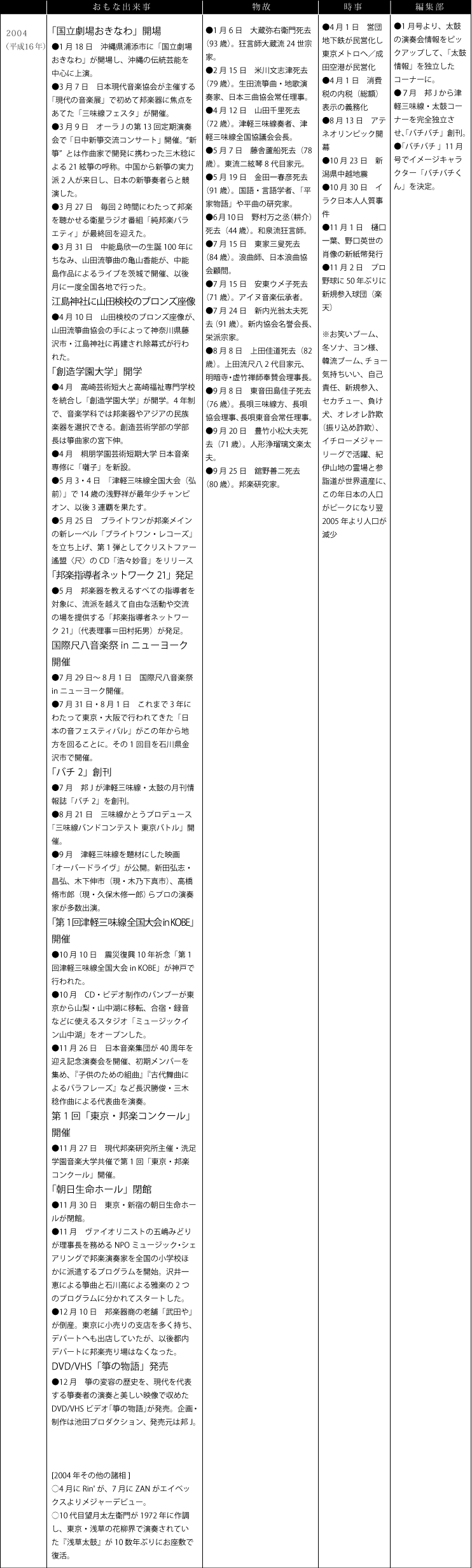
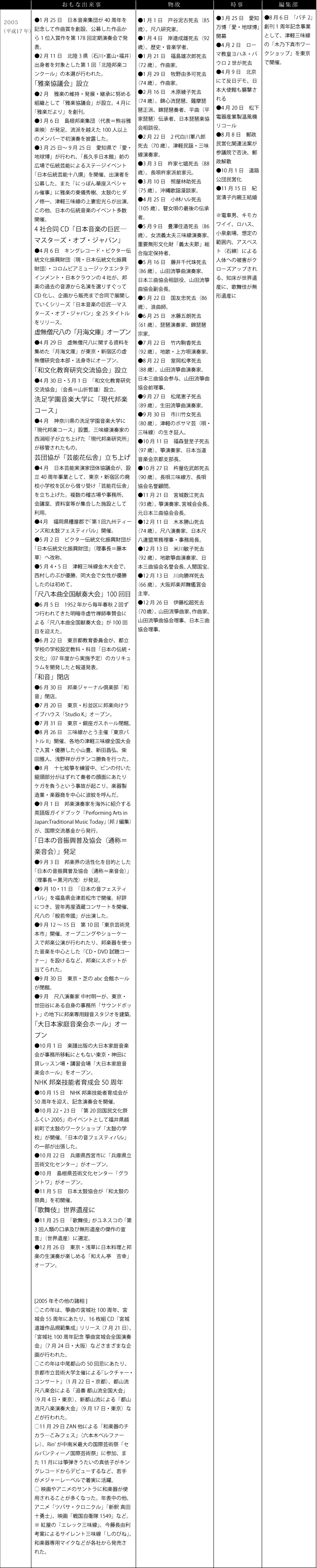
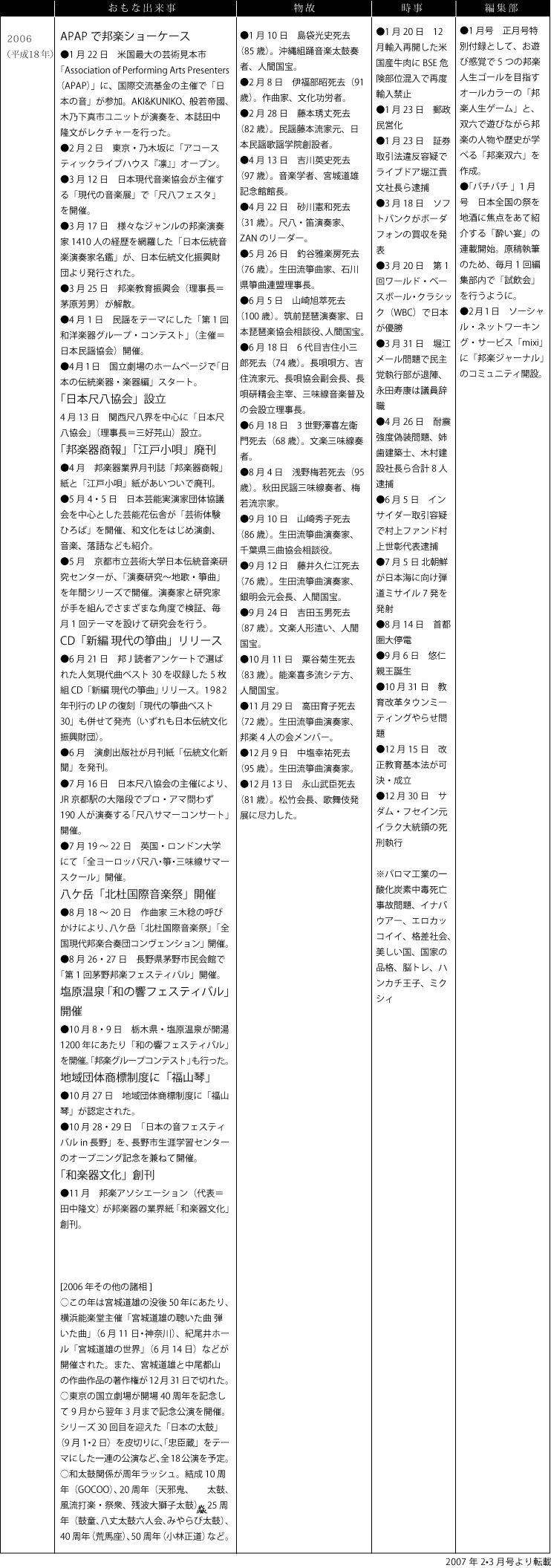
当サイトに掲載されている記事、写真、映像等の素材を無断で複写・転載することは著作権法上禁じられています。